夜な夜な、私と母の二人で、「逃げ先」を相談する日々。父には内緒で、二人だけでヒソヒソと話し合っていた。
反抗心とかから、父に内緒にしていたというわけではなかった。ただもう、これ以上は無理だよね、と半ば諦めていた。父にはまだ仕事があり、その仕事先に通勤するにはこの家が圏内ギリギリだった。でも私は、もう関東地方は空気が悪くて駄目だろうと思っていた。
なら、私一人で行くしかない。それで“一家離散”となるのなら、それはそれで仕方がない。
ある意味私はもう、完全に開き直っていた。ここから逃げ出すことしか考えなかった。ごみ焼却場の空気で廃人になるのは御免だ。
と、ある晩いつものように、母と二人で相談していると、ふいに父がやって来て、
「ねえ、二人で何相談しているの?
俺だけ除け者にしないで、ちゃんと三人で話し合おうよ。家族なんだから」

そう言った。私はびっくりした。あの父がこんな、こっちに頼むような口調で物を言ってくるなんて。
何しろ天正十四年(1925年)生まれの父である。地震雷火事親爺、ではないが、一昔二昔前の“恐い父親”というところが濃厚にあった。異を唱え口答えすると十倍くらいになって返ってくる。母に対してはそうでもなかったが、娘の私に対しては基本「~しろ」と命令調で物を言うのがまあ普通だった。
その父が、こんな気弱な、「~しようよ」口調で言ってくる、なんて。まあ。
父がどういう心境だったのかはわからない。が、このままでは家族がバラバラになるぞ、というある種の危機感は抱いていたのかもしれない。私が目の色を変え、半ば開き直っていることにも脅威を感じたか。あるいは単純に、母と私二人だけで結託しているらしきことが、つまり自分だけ排除されていることが、かなり身にこたえたのかもしれない。





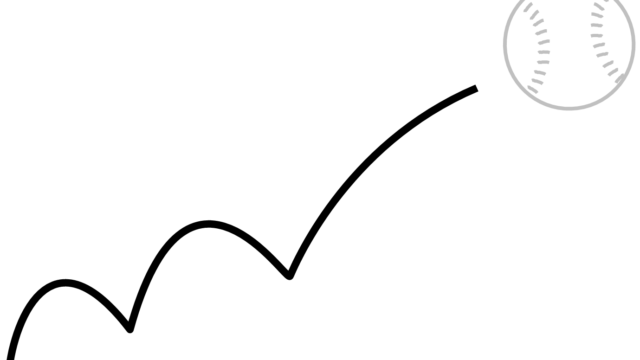





コメント