しつこく除草剤グリホサートの話を続ける。
必要があってグリホサートを使用しているのではない。グリホサートを大量に使うために必要が生み出されている」と前回書いたのだが、その最大のものが「遺伝子組み換え食品」(GM食品)である。
「遺伝子組み換え食品」とは、皆さん御存知の通り、農産物の遺伝子を人工的に操作して組み換えを行った食品のこと。代表的なのはトウモロコシ、大豆、てんさい、菜種油や綿実油などで、アメリカ産のこれらは80%~90%が遺伝子組み換え種になっている。

ではどのような「効果」を持たせるために、遺伝子組み換えを行ったのか?といえば、除草剤グリホサートをかけても枯れないように遺伝子を組み換えてあるのである。これを「グリホサート耐性」という。
というのもグリホサートは「非選択性」の強力な除草剤なので、これをかけると何でもどんな植物でも簡単に枯れてしまうのだ。それでは農業の分野では使えない。だから農産物の方の遺伝子を操作して耐性を持たせた、というわけだ。
『雑草だけ枯らせるから、農作業が楽になったことは間違いない。土壌流亡を防ぐ不耕起栽培農法もグリホサートに完全に依存しているから、それなしでは難しい。けれども重要なことは、耐性病や栄養価を高めるために遺伝子組み換えがなされているのではないことだ。まず除草剤ありきで、それを売るために後から遺伝子組み換え作物は登場してきた。話が逆なのだ』 (傍点引用者)『タネと内臓』吉田太郎著 築地書館 2019年第2刷 P41より引用)
遺伝子組み換え食品は、グリホサートを大量使用するために開発された。グリホサート耐性を持たせているのでこれらの農作物にはグリホサートがじゃんじゃん使われ、当然残留濃度も非常に高い。一応、日本も含める各国に残留濃度基準値はあるが、それもアメリカの匙加減一つだ。恐喝外交はトランプ政権に始まったことではない。
実際2017年に、日本のグリホサート残留基準は大幅に引き上げられた。改正前は5ppmだった小麦は一気に6倍の30ppmに、ライ麦は0.2ppmから150倍の30ppm、ソバも0.2ppmから150倍の30ppm、といった具合だ。残留基準値などあって無きがごとしだということがよーーくわかる。
ちなみにこの2017年の改正、12月25日のクリスマスの日に行われたそうだが、厚労省の担当者はその後内輪の席で、
「クリスマスプレゼントでした。」
とか言ったとか。アメリカに? それともその後自分の天下り先の化学企業に? 厚労省に私たちの健康を守る精神は、果してあるのか。ひとっかけらもないんじゃないだろうか。(『本当は危ない国産食品』 奥野修司著 新潮新書 2021年第2刷 P131より)
そういった小麦やソバ、“粉モノ”だけを気を付けていたらいいのかと思いきや、残念ながらそうではない。前述した遺伝子組み換えトウモロコシや大豆、てんさい、菜種油などは、現在加工品に見えない形で巧妙に入れられている。2023年に食品の表示法が変わり、「遺伝子組み換えでない」表示が実質骨抜きにされてしまったのだ。
また以前から外食産業においては、食品表示の義務がなく何の表示もない。
よほど意識しなければ、知らないうちに私たちは遺伝子組み換え食品やグリホサートを口にしている。否、食べさせられているのだ。





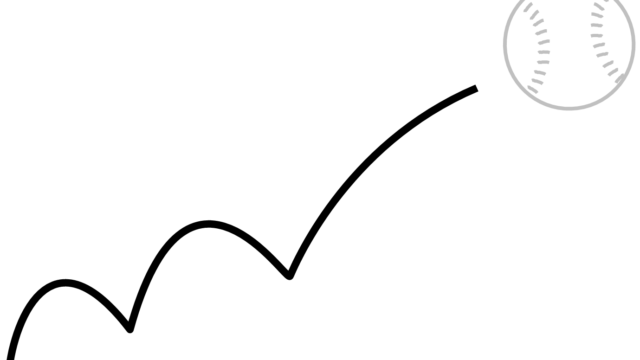





コメント
タリカさん、ブログ管理人さん、こんにちは💞残暑厳しいですが、いかがおすごしですか?私は相変わらず低空飛行✈ですが、なんとか生きています💦
環境問題を考えるのに役立つ無料オンライン講演のお知らせです🙌皆さん、ぜひ視聴しましょう!!
有害化学物質削減ネットワーク(Tウォッチ)による無料オンライン講演のお知らせ
「暮らしの中の化学物質の課題を考える2025」
開催案内
2001年度から開始されたPRTR制度を市民に定着させることをめざして、有害化学物質削減ネットワーク(Tウォッチ)を結成して、20年を超えました。この間、日本の環境中に排出される有害化学物質の量は半減しました。とはいえ、それで化学物質による環境リスクが半減したといえるかは難しいです。私たちの暮らしの中に使用される化学物質による、新たな環境汚染や人体汚染が問題になってきています。
2025年度の公開講座では、PFAS(有機フッ素化合物)や農薬、香害から私たちの暮らしをどう守っていけばよいのか。2023年度から対象物質の見直しが行われたPRTRデータをどう活用していけばよいのか、最新の情報を提供します。あわせて、8月に開催された国際プラスチック条約のINC5.2の結果について、報告いただき、暮らしの中の有害化学物質をどう減らしていくのか考えていきたいと思います。
昨年同様、オンライン開催とし、子育て世代の方が参加できるように平日の午後に設定しました。ご自宅等から気軽に参加することができますので、奮ってご参加ください。
第1回 プラスチック条約INC5.2の参加報告 条約交渉の課題 9月24日
第2回 日本におけるPFAS(有機フッ素化合物)汚染の現状と課題 10月22日
第3回 子どもの香害被害の現状と課題 11月26日
第4回 対象物質見直し後のPRTRデータをどう読むか 12月24日
第5回 農薬再評価制度の現状と課題 1月28日
https://toxwatch.net/seminar/2025-9/