今私の家の畑には、麦が穂をつけ風にゆられている。小麦ではなくライ麦で、食べる用というよりは土質を良くする緑肥として去年種を播いたのだが、いいかげんにバラ播きしたにしては実によく育っている。その青々とした、日ごとにすっくすっくと育ってゆく麦を見ているのは、なかなか気持ちがいい。いい眺めだなぁ、と思う。

驚いたのは、麦を播いたところにはほとんど雑草が生えないことだった。他の畑のところには、アレチウリやオオブタクサ、棘のあるつる性のもじゃもじゃした雑草が、取っても取ってもすぐ生えてくるのに、ライ麦のところにはまったく生えないのだ。たぶん麦の根に付く土壌菌、根瘤バクテリアが土の質を、麦の好むものに変えてくれているのだろう。根瘤バクテリアは土壌に窒素を固定してくれる。麦が緑肥として効果があるのはそのためだ。
このように麦は、本来除草剤など要らない品種のはずなのだ。なのになぜ、麦から除草剤グリホサートが検出され出てくるのか。
日本は国産小麦の自給率が低く、ほとんどを海外から輸入しているが、アメリカ産、オーストラリア産、カナダ産の小麦からは高濃度のグリホサートが出てくる。その検出率はアメリカ産で98%、オーストラリア産で45%、カナダ産に至っては何と100%だ。
『本当は危ない国産食品 「食」が「病」を引き起こす』 奥野修司著(新書選書 2021年第2刷)の中で、分子生物学者で「遺伝子組み換え情報室」代表の河田昌東氏は次のように述べている。
『信じられないかもしれませんが、収穫直前にラウンドアップを撒いて小麦を枯らすんですよ。それから収穫すると、自然に枯れるのを待つよりも効率が良くて収量がいいんですね。この方法を、収穫した後に防虫や防カビのために農薬を撒くポストハーベストに対して、プレハーベスト(収穫前)といいますが、カナダ産やアメリカ産の小麦からはほぼすべてから出ます』 (前掲書 P102・P104より)
小麦の乾燥の手間を省くために、グリホサートを撒くというのだ。何という恐ろしいことを・・・!
実際今日本で流通している、大手企業―山崎製パン、フジパンなどの食パンを分析してみると、グリホサートが検出され出てくる。逆に国産小麦を使用している、ザクセンやPascoの食パンからは検出されてこない。(同P145表)かなりはっきりしている。
ただCS患者の私から言うと、「国産小麦使用」と「国産小麦100%使用」では、食べてみたとき明確に差があった。前者は何かちょっとおかしいのだ。たとえ国産小麦を全体の10%しか使っていなくとも「使用」とは書けるわけで、そこは目を光らせておかねばならない。
また以前、「国産小麦100%使用」のパスタを食べた2~3時間後、突然差し込みのような激しい腹痛に襲われたことがあった。左脇腹の上の方の腸辺り。油汗が出るような痛みで、ちょっとどうしようかと思った。「パスタで食後激しい腹痛」という人はけっこういるらしく、これなども腸内善玉細菌を殺すというグリホサートの仕業かもしれない。あの激痛は、腸内細菌たちの断末魔の悲鳴だったのかも。
平然と人の口に入るものに、除草剤をぶっかけるというそのやり方。その暴挙。それは決して、必要にせまられてやっていることではない。小麦を乾燥させるなら自然乾燥でも、脱穀後の機会乾燥でも実はできる。
つまりこれは、除草剤グリホサートを大量に使うために行われていることなのだ。必要があっての使用ではない。逆だ。使用するという前提がまずあり、その後で必要が生み出されていく。大量の除草剤を消費させるために。
このレトリックに、私たちはもうそろそろ気が付かなければならない。同じことがあちこちで繰り返されているからだ。私たちの健康は今や、最大の「消費物」になりつつある。





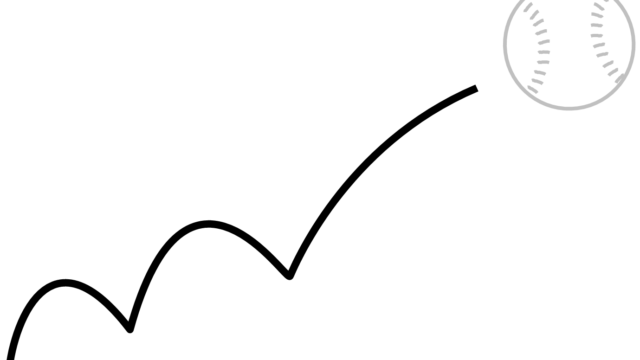





コメント